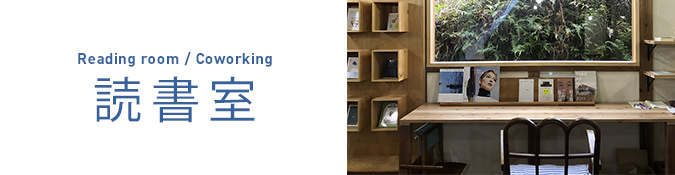「野生」のみつばちが居つく
- 2017.02.01
- by Yukio
前回のコラムで日本みつばちは「野生で生息しているみつばち」であるとお話しましたが、今回は「野生」なのに「飼育」しているというところをもう少し。
まず、「野生」とは?
動植物が山野に自然に成長・生育していること。
という意味だそうで。その反対は「飼育」「家畜」。
「野生」であれば自然界の中でも生きていけますが、「飼育」「家畜」であれば、人の手が届かないと生きていけないのです。
野生のみつばち
日本中のいたるところで生息しています。その場所は、木の洞(うろ)、石碑の隙間、コンクリートの隙間、家の屋根裏など。ある程度中が広い密閉空間で、かつ小さな入口があれば巣を作り、そこで営んでいるのです。
私も昨年夏、山奥の道路沿い、このコンクリートの隙間に出入りしているみつばちを見かけました。

他にも、近くの神社にある石碑

この石碑の割れ目からもよくみつばちが出入りしています。
(※写真は冬に取ったので、みつばちはおりませんが。)


自然界、人工物の隙間、どこでも生息して、生きていきますという感じです。
ここから、居を移して、山の中に引っ越しても、その自然の中で生きていけるみつばちなのです。
(一方のセイヨウミツバチは人間によって完全に「飼育」されないと、自然界では生きていけないみつばちなのです。)
野生のはちを飼うというよりは
日本みつばちを飼っているというよりは、彼らがその環境(巣箱)を気に入って、居ついてくれてるだけ。私たちはそのような感覚です。

気に入らなければ突然どこかに引っ越しするし、時には、自然の力によって淘汰されて消滅することもあります。
ただ、彼らに来てもらうために、居ついてもらうために、なりゆきに任せるのではなく、彼らが気に入るような巣箱を作って、彼らが気に入りそうな場所に巣箱を設置する。そんな努力が必要です。
もちろん、居ついたあとは巣箱の掃除なども行い、日々、気にかけてあげることも大切。
(日本みつばちに来てもらうための方法はまたの機会に。)
春の分蜂(巣別れ)の時期に、みつばちたちにこの巣箱を選んでもらって、ここに住んでもらう。その場所が気に入れば、そこに住み着いてくれるのです。
そして、蜂蜜を分けてもらうことにもつながっていくのです。
ちなみに、うちの父親は
「あいつらはわしの子分や。わしが農作業しとるときに、働いとるんや。だから、掃除とか面倒見てやらなあかんのや。」
と言っておりました。
父親なりの愛情表現だと思います。